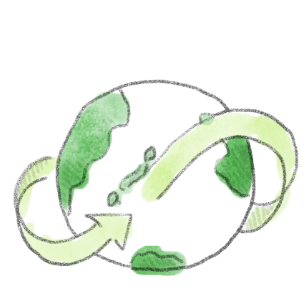Web Magazine
柿の木便り
社会の中で生理が「ないもの」にされているのはなぜ? 男性映画監督のある視点

PMSや生理痛があったとしても、仕事も家事も休むことなくいつも通りにやり過ごす。少しずつ認知が広がっているものの、まだまだ社会でも家庭でも、生理は「ないもの」とされがち。
生理とはなにか? どうして生理はタブー視され、隠されるのか?
そんな問いを持った、映画監督の朴基浩さんは、2020年に『LOOKING FOR THAT-アレを探して-』を制作。発達障害の女性、セックスワーカー、PMSに悩む女性とそのパートナー、病気で子宮を摘出した女性、閉経した女性……15人の生理にまつわる証言をとらえた約60分のドキュメンタリーです。
生理の映画を巡る想いと、制作を通じて行き着いた朴さんの視点を紐解きます。
女性たちの声と、生理の疑似体験。生理の映画を撮り始めるまで
──そもそも朴さんが、映画の主題である「生理とはなにか?」という問いに行き着くまでにはどんな過程があったのでしょう?
朴: 男性の自分がどうして生理の映画を撮ったのか、とよく聞かれるんですが、個人的にずっと「生理」が気にはなっていたんです。4人きょうだいで育ち、兄が一人、姉が二人いて、生理が割と身近にあって。うちは性にオープンな家庭で、高校でアメリカに留学する際には、母親に「イギリス紳士のマナーや」ってコンドームが入ったご祝儀袋を手渡されたこともあったんですよ。「行くのはアメリカやけどな」って思いましたけど(笑)。それくらいオープンなのに、それでも生理のことは母も姉も「アレ」と呼んで隠語化されていて、自分にはその感覚がよくわからなかったんです。

生理ってなんなんだろう?という単純な興味を引き伸ばすきっかけになったのが、上の姉の第二子の出産に立ち会ったこと。一部始終カメラを回していたんですが、生まれるまでは強烈な痛みに対する叫びが響き渡っているんだけど、生まれた瞬間に、妬みも嫉みも恨みもない平和で穏やかな喜びに包まれたような気がしました。この経験のあと、ふと社会を見渡したときに、妊娠・出産には生理が紐づいているはずなのに、どうしてタブー視されているんだろう?という問いが深まっていったんです。
──映画を撮る前に、アンケート調査を行い、ナプキンを装着して生活をしたそうですね。
朴: 生理の映画を撮ろうと決めてから、SNSを通じて生理にまつわるアンケートを募集したら、100人を超える女性から回答をもらって。ものすごくバラエティに富んだエピソードが溢れていたんです。一人ひとりこんなに違うんだ、一般化できない事象だなと感じました。男性の自分は生理を身をもって経験できないんですが、疑似体験してみたいと、一週間ナプキンをつけて生活してみたんです。初めはナプキンに水を垂らして、ドロッと感を出すためにシャンプーとリンスをかけてみたけどいい香りがしちゃって(笑)、最終的にはトマトジュースに行き着きました。
──トマトジュースをこぼしたナプキンをつけて生活してみて、どうでした?
朴: 一週間の平均的な経血量を調べて、取り替えてはこぼす生活をしていたんですが、手間もかかるし、会議中とか、漏れないかな、臭わないかな、と心配になった。ここにPMSや生理痛など精神的・身体的な不調が伴うのは、大変だなって。なのになんで社会は「ないもの」として扱うんだろうってやっぱり思いましたね。
その後、性教育の普及に取り組むNPO法人PILCONの染矢さんが女性たちを集めてくれて、そこでリアルな声を聞いたらアンケートと同感覚の言葉が紡がれていて、本格的に撮影を始めた感じです。
生理がタブー視される背景には「男性優位の社会」があるという気づき
──映画を拝見して、私は女性ですが、感覚がわかる部分もわからない部分もあって、やっぱり生理は人それぞれ個別的なものであるし、女性同士でもあまり語り合ってこなかったなと思います。オープンにそれぞれの生理を語る女性の言葉も印象的ですが、この映画は男性である朴さんが、生理がタブー視される背景には「男性優位の社会」があることに気づいていく、男性としての当事者のドキュメンタリーでもありますよね。
朴: まさに、撮影を進めて女性に話を聞くたびに、どんどん自分の「男性性」を否定して、自己嫌悪に陥っていきました。これまでお付き合いしてきた女性や現在のパートナーとの関係性を振り返って、PMSだったのに逆ギレしちゃってたかもとか、性行為で無理をさせてなかったかとか。特に取材させてもらったセックスワーカーの方の「半分家政婦、半分風俗嬢」という言葉にはガツンと頭を殴られたような感覚でしたね。言葉は強いけど、家事をやってもらって性行為を求めて、少なからず思い当たる節があるんじゃないか、と。認めたくはないけれど「男性性」を狡猾に利用している自分に気づいて、自己否定しました。

──その気づきから、見える景色や実際の行動が変わっていったことはありますか?
朴: 自分ごととなるとうまくはできないんですが、パートナーに対しては、なるべく話を聞くようにしています。パートナーのホルモンの変化に気づくためにも、生理用品は僕が買いに行くようにしていて。家事も下手くそでも自分がやるようにしていますね。パートナーは自分がやったほうが早いと思っているけど、頼むからやらせてくれと。当たり前のようにやってもらうと、甘えて成長できないんで。料理もつくらなくていいし、極力座っててほしい。いつもそれで喧嘩になるんですけど。
社会に対しては、ふとしたときに、これって男性目線じゃない?と疑ってブレーキがかかるようになりました。例えば、細かいことですが、飲みかけのお茶をちょっとだけ残すとき。最後は女性が片付けてくれるという甘えがあるんじゃないかと思うんで、残さずに飲み切って片付けまでやるとか。以前仕事関係の方々とBBQをしていたとき、女性ばかりが片付けをしていて、年上の男性に「おかしくないですか?」って意見したこともありました。そうやって、自分が気づいたことや違和感はできるだけ口にして、“当たり前”に抵抗していく、孤独な戦いを実践中です。
違和感をスルーせず、身近なところから“当たり前”の風景を変えたい
──周囲が“当たり前”に思っていることに対して、違和感をスルーせずに意見することは簡単にできることではないですよね。いまだけ自分が我慢すればいいと思ってしまいがち。朴さんが「孤独な戦い」ができるのは、どうしてなんでしょう?
朴: これは僕の国籍に関わることなんですが、在日朝鮮・韓国人なんで、不当な差別を受けることがあるんですよ。手続き一つとってもしなくていい努力を強いられることもあるし、いまだにネット上で暴言をぶつけられることもある。僕自身は現段階では、子どもを持たない選択をしていますが、姉の子どもは日本の学校に「朴」という苗字で通っています。彼らが大人になってもこの不当な差別が続くのかと思うと、どうしても嫌だ。だからそれまで「そういうものですよね」と飲み込んできたことに対して「おかしいですよね」と怒るようになった。一言でいえば、めんどくさいやつになったんです。誰かが発信しないと、不当なことだと認知されないんで、「まあいっか」とスルーせず、波風立てる「孤独な戦い」を僕は選んでいます。

──さまざまな立場や意見の人がいる中で、今回の映画含め、「男性優位の社会」に対して当事者として発信していくことには、勇気や覚悟がいるようにも思います。
朴: 僕が育ってきた家庭環境やコミュニティは、圧倒的に男尊女卑で、母や姉が苦しんでいるというか無意識に抑圧されているような姿を見てきました。法事や葬式でも、女性は台所でずっと動いていて、男性は居間でずっと座って駄弁っている。それが当たり前の風景だったので、今でも気を抜くと父のようになろうと思えば簡単になれちゃうと思うんです。一方、思春期に留学して過ごしたアメリカの家庭では、男性も女性と同じようにずっと動いていた。その姿もインストールされていて、僕はやっぱりこっちを選びたい。母や姉のようになかなかごはんにありつけない女性をこれ以上増やしたくないんです。
僕は映画を撮る前、10代の若者の生きづらさを解決するNPO法人の共同代表をしていたんですが、社会を変えるのって大変なんですよ。大きな目標を描いてそこに向かっていくのは、体力も気力もいる。いろんなステークホルダーに頭を下げて、あるとき支援者の方から「公務をしているみたい」と言われました。それも大事な取り組みの方法なんですが、今は一旦おやすみして、観る人の視点を変えられるかもしれない芸術、映画づくりに励んでいる。根本にある想いは変わらないけど、長く続けていくために、戦い方を変えたんですね。いまは家族やパートナー、周りに困っている人がいないか、身近なところから違和感をスルーせず差別の芽を潰していけるか、が勝負だと思っています。
「男性優位の社会」の当事者として、想像力を持って、小さな変化を重ねていく
──自分自身や身近な人が感じる困難は、社会課題とも地続きにありますもんね。
朴: 実はこの映画は、下の姉のために撮ったようなものなんです。というのも、姉はずっと生理がなかったんですね。男尊女卑の家庭環境の中で、兄と姉が家を出て、僕は逃げるようにしてアメリカに渡った。そのときにきょうだいのうち一人家庭に残った姉の生理が止まったという話を後から聞いて、ずっとどこかしらで贖罪意識があったんですよ。それで生理のことが気になっていたんだと思います。結局いまも姉は観てないんですけど(笑)。余談ですが、この映画を撮り終えて大分の別府で編集作業をしているときに、姉から妊娠報告を受けたんです。それまで生理がなかったのに、まさかの妊娠。こんなこともあるんだって、驚きました。
──私も生まれつき生理がない原発性無月経で妊娠をしたんですが、不思議な奇跡ですよね。女性自身がそれぞれ特有の性の悩みを抱く中、朴さんが男性の当事者として「男性優位」の社会であることに気づいて、身近な、日々の生活から変えていこうとしていることは小さな希望だと感じます。

朴: 僕自身もまだまだしょーもないプライドが顔を出すこともあるし、マッチョな世界で下駄をはかされていることをつい忘れてしまうこともあります。でもこの映画を撮ってよかったと思うのは、ひょっとしたらあの人もそうかもしれない、と想像力が働くようになったこと。例えば一緒に仕事をする女性のパフォーマンスがよくなかったとき、「なんでこんな調子が悪いの?」と思ってしまっていたところが、「今日は調子が悪いのかもしれない」という仮説を立てられるようになった。見える世界の視点が増えて、相手に対してやさしい気持ちになれるんです。ステップバイステップでそういう小さな変化を積み重ねていくしかないと思っています。
──一歩一歩、ですね。これから取り組んでいきたいテーマはあるんでしょうか?
朴: 実はいま、「包茎」をテーマにした映画を撮っています。包茎の手術を受けて失敗して、性感を失ったある男性を2年間追っているんです。そこにも「男性中心主義」の考え方が垣間見えて、今回のテーマともつながっていると思いますね。出来上がったら、ぜひ観てほしいです。
text by 徳 瑠里香 photo by 三浦咲恵

朴 基浩 (ぱく・きほ)さん
映画監督
立命館アジア太平洋大学(APU)卒業後、通信制や定時制の高校生が卒業後に進路未決定にならないための活動を展開すべく、NPO法人D×P(現:認定NPO法人D×P)を設立。学校とのプログラム連携、TEDスピーチへの出演、世界会議への日本代表として出席。2015年9月に代表を退任後、映像制作活動をはじめる。監督を務めたCMが宣伝会議主催「ものがたりアワード」にてグランプリを受賞。現在は多ジャンルの映像制作や構成を手がける。